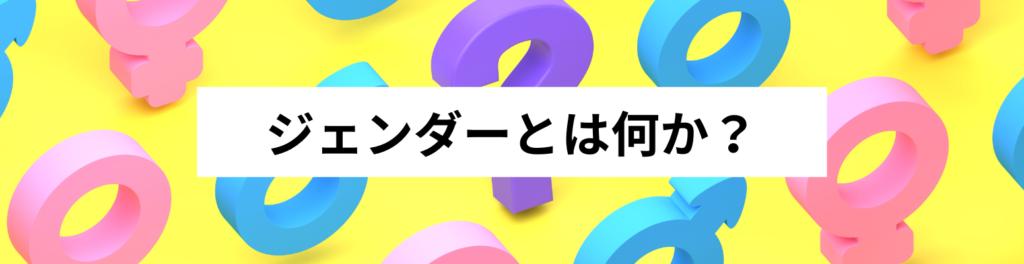

解説:衛藤幹子(法政大学 名誉教授)
ジェンダーという言葉、今日では頻繁に見聞きし、私たちの日常にかなり浸透しているようにみえます。しかし、ジェンダーは、単に社会的な性差や、セックスに代わる性別を表す言葉にとどまるものではありません。ジェンダーについて知っているようで、しかし改めて問われるとよく分からないといった方が多いのではないでしょうか。そこで、ジェンダーとは何か、そのごく大まかな意味と用法を説明してみたいと思います。
ジェンダーは言葉であると同時に、思考や表象、認識、規範を内包する概念である
たとえばジェンダー平等/不平等、ジェンダー・ダイバーシティ(多様性)、ジェンダー・ステレオタイプ(固定観念)、ジェンダー役割分担(gender division of labor)といったように、規範や観念を表す用語として用いられることに表れています。また、単独で使われる場合でも個人のアイデンティティ、社会関係など何らかの価値を含む言葉として機能します。さらに、人文・社会科学の分野では、人間関係、集団、事象を分析するための重要なツールとして使われ、ジェンダーをアプローチ方法として取り入れた研究が盛況を呈しています。もっとも、ジェンダーをめぐるこうした動向は、ここ半世紀ばかりの間に起こったことです。
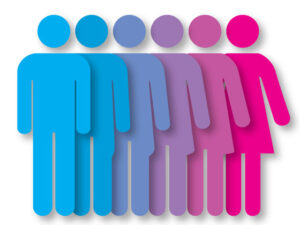
両端が男性性と女性性のプロトタイプ。
出典http://www.naturalwisdomcounseling.com/blog/2016/5/1/confessions-of-a-non-binary-therapist
「ジェンダー」の再発見
「ジェンダー gender」には二つの語源があリます。一つは、種類や種別、性別、また男性性や女性性の質、人種などを表す中世フランス語のgenre、もう一つがラテン語の人種、種類、文法上の性別を意味するgenusです。英語のジェンダーは後者の用法を継承し、フランス語、ドイツ語、英語などに見られる名詞や形容詞、所有格の男性形、女性形、中性形といった文法上の性区分を示す用語として15、6世紀頃より使われるようになったと言われています。文法用語のジェンダーは注目度の低い、地味な言葉です。
ところが、1950年代から60年代のアメリカ合衆国で、発達性科学者のジョン・マネーと精神医学者ロバート・ストーラーが、それぞれ別の研究ではあったのですが、生物学的な性別(sex)とは異なる、社会環境の中で形成される性別を表す用語として、ジェンダーを使いました。とくにマネーは、「ジェンダー・アイデンティティ」と「ジェンダー役割」という用語を創出し、今日のジェンダー概念の形成に大きく貢献しました。ジェンダー・アイデンティティとは、人が男性あるいは女性と自らのジェンダーを認識する、自己同一性の基本的要素です。マネーによると、人はそのアイデンティティにもとづいて男らしさ、女らしさの社会規範に一致するように行動し、マネーはこれをジェンダー役割と呼びました。
折しも1960年代後半から70年代、北アメリカと西ヨーロッパではフェミニストの社会運動が湧き上がっていました。「ジェンダー」は、家庭に留まって家族の世話をするのが女性の役割とする社会通念に異議を唱え、男性中心社会からの解放を求めていたフェミニストの心を捕え、生まれながらの性とは異なる後天的に形成される性役割を表す用語として英語圏のフェミニスト学者の間に急速に広まりました。やがて、フェミニズムの枠を超えて、国際機関、政府、社会組織、メディア、市中の人びとにも受容され、私たちの生活の中に頻繁に登場する言葉になったのです。20世紀の「ジェンダー」の生みの親はマネとストーラーですが、この新しい用法を社会的概念として確立し、世の中に浸透させたのはフェミニストの功績と言えるでしょう。
ジェンダーの定義
ジェンダーを一言で定義するのは非常に難しいのです。学者によって定義が異なります。また、時代ごとに変化しています。たとえば、私がジェンダーを研究し始めた24、5年前、ジェンダーは、生まれながらの性/性別(sex)と対比して説明され、後者が不変かつ不可逆的であるのに対し、前者は変更可能であり、可逆的なものだと説明されることがありました。しかし、今日、この説明は間違いです。というのも、性別も不変ではなく、そのうえ男女という二つの性にキッパリと割り切ることができないからです。たとえば、身体の「男性 male」性と「女性female」性の濃淡には個人差があり、男性性あるいは女性性の要素だけの人もいれば、両方が重なる人がいます(注1)。また、個人の中でも第二次性徴と老化によって濃くなったり、薄くなったり変化します。こうした性(sex)の多様性と変化については「性スペクトラム」の研究が明らかにしています(注2)。
さて、ジェンダーの定義ですが、ここでは、古い文献で恐縮ですが、30年間のフェミニスト研究者の議論を踏まえ、しかも日本でも馴染みの深い2002年のR・W・コンネル(注2)の定義を引用したいと思います。コンネルは「ジェンダーは生殖領域を中心とした社会関係の構造であり、同時にこの社会関係の構造に支配され、生殖をめぐる性の区別と社会過程を接合する実践でもある」としています。少し言葉を足すと、ジェンダーは生まれながらの性別とは無関係ではなく、生物学的な差異や特徴、とりわけ女性の生殖機能がジェンダーを基礎付けているというわけです。つまり、こうした生物学的な違いが根底にあるがゆえに、私たちは男女の役割の違いや両者の序列化をあたかも自然な摂理であるかのように思い込んでしまうのです。
ジェンダーの用法
現在、ジェンダーがどのように使われているか、その用法を示したほうが、この言葉の理解が進むかもしれません。4つに分けてみました。
① 性自認
自分の性別をどのように認識するのか、男性、女性、それ以外など、自己の性認識を表現する場合にジェンダーが用いられます。多くの人は身体の性別と自分自身の性別認識が一致していますが、そこに不一致をきたす人は決して少なくありません。トランスジェンダーはよく知られていますが、そのほかにも男女という区切りではしっくりこず、どちらでもないとする人、あるいは区分自体を否定する人、両方を認める人など実に様ざまです。岡山大学の調査では、日本の場合生まれつきの性別に違和感を持つ人(医学界では「性別違和」と呼ばれています)は人口の0.3から1%と推定されています(注4)。
② 「性別sex」に代わる性別の呼称
性自認は、自分は何者なのか、個人のアイデンティティと深く関わっています。アイデンティティは人にとって言わば(社会的)存在の基盤です。アイデンティティを見失えば、自分という存在が足下から崩れ落ちてしまいます。このような性自認の重要性を考えるならば、生まれながらの性を表してきた「性別sex」を性別の呼称として使うのは適切とは言えませんし、ジェンダー・ダイバーシティが推奨される今日ではもはや時代遅れです。
こうしたなかで、メディアにおける表現や個人情報を記入する際の性別欄において、「性別」ではなく「ジェンダー」が用いられることが増えています。一般のアンケート調査では「ジェンダー」がかなり浸透していますが、政府関連の文書や調査ではまだ「性別」を使用しているようです。もっとも、いくつかの国では、パスポートの性別記載欄に「ジェンダー」を使用し始めています。マレーシア、ソマリアのパスポートでは「ジェンダー」が採用されています。
欧米諸国を中心に、性別欄は依然「sex」を使用していても、その選択肢に男性(male)、女性(female)に加えて、「そのほか(other)」もしくは「どちらでもない(X)」を設け、性自認の多様性を担保する国が増えています。
③ 社会的かつ文化的に形成された固定的な観念の表象
これはとりわけフェミニストにとって重要な用法です。フェミニズムは、女性ゆえに押し付けられる役割、女性ならこうすべきだという規範や求められる振舞いなど固定化された観念に異議を唱え、その是正のために闘ってきました。フェミニストは、こうした観念は女性が生まれながらに運命づけられたものではなく、社会的かつ文化的な作為による後天的産物だと考え、それを示すためにジェンダーを冠したのです。
たとえば「男性は外で仕事をし、女性に望ましいのは家庭で家族の世話をすること」、「育児は女性の責任」がジェンダー役割分担、「男性は逞しく能動的、女性は優しく控えめであるべき」はジェンダー規範です。今日、「女性の居場所は家庭」と言う観念は通用しなくなっているようはみえます。しかし、この観念は「他者をケアする仕事(保育士、看護師、小学校の教師など)」への女性の集中、出世や昇進における男性優先などに現れ、まだ生き続けています。
男女に振り分けられる固定観念は、いうまでもなく男性にも強い圧力として作用します。男性の生きづらさは、男性に向けられるジェンダー・ステレオタイプから生じている面も少なくないのではないでしょうか。言うまでもなく、トランスジェンダーやそれ以外のジェンダーの人びとがこうした固定観念に一層強く苦しめられています。
④ 権力関係を分析する学問的アプローチ
フェミニストは、家庭や職場など社会における男女の関係を構造化された権力関係と捉えました。そのため、ジェンダーには社会集団間の支配と従属、抑圧被抑圧の権力関係を炙り出すというパースペクティブが埋め込まれ、研究者はこの視座によって社会の様ざまな事柄を分析するようになりました。しかも、社会集団間の権力構造という観点に立てば、不平等な関係は男女に限らず、性自認と性的指向性は言うに及ばず、人種、民族、宗教などにおいて少数派の集団の問題にも切り込むことができます。つまり、社会に埋め込まれた社会集団の間の権力関係を可視化できるのです。
私は、学問的アプローチとしての「ジェンダー」が際立つのは、確立した通説と所与とされてきた常識を疑い、批判し、それらとは異なるばかりか、ときに対立さえする見方、考え方を提示できる点にあると考えています。ジェンダーはフェミニストならずとも魅力的な分析概念ではないでしょうか。事実、人文・社会科学の様ざまな分野で、「ジェンダー」アプローチが試みられています。私は、政治学の分野でこのアプローチを使ってきました(注5)。手前味噌になりますが、他の人とは違う、面白い研究ができたと自負しております。
さて、私はジェンダー・アプローチを専ら人文・社会科学に限られるのではないかと考えてきましたが、これも時代遅れになりました。というのも、2010年前後から、科学・技術の研究開発にジェンダー・アプローチを取り入れる「ジェンダード・イノベーションgendered innovations」という考え方がアメリカのプリンストン大学と欧州委員会から提唱されているからです。ジェンダーの考え方は、科学・技術という所謂理系分野にも適用可能なのです。しかし、考えてみれば、科学・技術の多くの領域には人間の営みや社会が関係しているのですから、ジェンダーの観点が入り込む余地は大いにあるわけです。
注2. 性スペクトラムに関しては、諸橋憲一郎『オスとは何で、メスとは何か?—「性スペクトラム」という最前線』(NHK出版新書、2022年)が分かりやすい。
注3. R.W. Connell (2002) Gender. Cambridge: Polity Press.
注4. 出典:https://www.okayama-u.ac.jp/up_load_files/press_r4/press20220615-1.pdf
注5. 政治学におけるジェンダー・アプローチの適用性にご関心のある方は拙書『政治学の批判的構想—ジェンダーからの接近』(2017年、法政大学出版局)をご参照いただきたい。
